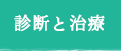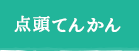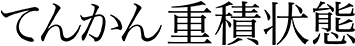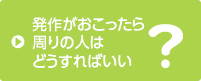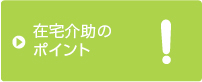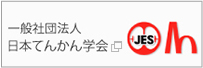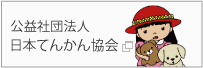てんかん重積状態とは
てんかん発作がおきても通常は数分間で自然に消退します。しかし、発作が異常に長引いたり、いったん発作が終わっても意識が戻らないうちにまた繰り返す場合は、てんかん重積状態といいます。てんかん重積状態とは、国際抗てんかん連盟(ILAE)が1981年に作成した分類によると,「けいれん発作が30分以上続くか、または、短い発作でも反復し、その間の意識の回復がないまま30分以上続く状態」と定義されています1)。
また、2012年に米国のNeurocritical Care Societyが発表したガイドラインによると、「けいれん発作が5分以上続くか、または、短い発作でも反復し、その間の意識の回復がないまま5分以上続く状態」と定義されています2)。
てんかん重積状態は、けいれん発作が続く「けいれん性てんかん重積状態」と、けいれん発作を伴わない意識障害(てんかん発作による)が持続する「非けいれん性てんかん重積状態」に分類されます。
1) Epilepsia. 1981; 22(4): 489-501. Bancaud J, et al.: Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. From the Commission on classification and Terminology of the International League Against Epilepsy.
2) Neurocrit Care. 2012 ;17(1): 3-23. Brophy GM, et al.: Guidelines for the Evaluation and Management of Status Epilepticus.
けいれん性てんかん重積状態
| 症状 | けいれん発作症状が持続、または意識の回復のないまま反復します。持続時間は30分以上と定義されることが一般的ですが、臨床現場では5分以上をてんかん重積状態と考えて治療を開始します。
|
|---|---|
| 原因 | てんかん重積状態や発作頻発を起こす原因として、小児では、熱性けいれん、脳炎、脳症、髄膜炎など、急性の原因が多くみられ、成人では、脳血管障害、脳腫瘍、脳炎、髄膜炎、頭部外傷などがみられます。てんかんの既往のある場合は、薬の飲み忘れ、睡眠不足、過労、月経、感染症などが誘因としてあげられます。 |
| 検査 | 検査は治療と同時に開始します。問診ができれば、けいれん性てんかん重積状態の原因疾患を推定することができます。発作を注意深く観察し、バイタルサイン(血圧、心拍数、体温、呼吸状態)を確認し、てんかん治療中であれば、抗てんかん薬の血中薬物濃度を測定します。血液検査、MRI/CTなどの画像検査、脳波、髄液検査などを実施します。 |
| 治療 |
|
非けいれん性てんかん重積状態
| 症状 | 脳波ではてんかん発作性異常を認めるものの、けいれん発作を伴うことなく意識障害が持続し、急性・遷延性(長時間にわたる)昏睡状態を示すことがあります。複雑部分発作あるいは欠神発作が長引いた状態ともいえます。非けいれん性てんかん重積状態の場合は、いつから始まったのか明らかでないものが多くみられます。その症状は多様で、凝視、繰り返す瞬目、さまざまな神経心理学的障害や認知・行動障害(失語や健忘など)・意識障害を呈します。
|
|---|---|
| 原因 | 新生児期、乳児期では、大田原症候群、点頭てんかん、Dravet症候群などが原因となります。小児期以降ではさまざまなてんかん症候群や脳症を原因とする場合や、抗てんかん薬を突然中断した場合にもおこります。脳炎、脳卒中や頭部外傷など、原因は多岐にわたります。 |
| 検査 | バイタルサイン(血圧、心拍数、体温、呼吸状態)を確認します。脳波所見は必須で、意識障害をおこしている患者では非けいれん性てんかん重積状態を疑って、なるべく早く脳波検査を施行します。 |
| 治療 |
|
てんかん重積状態の予後
てんかん重積状態の予後は一般的によくないのが現状です。背景にある疾患が脳卒中や中枢神経感染症など重篤な場合は特に深刻です。脳機能障害や精神機能障害が残ることもあります。予後不良の原因が、てんかん重積状態にあるのか、背景の疾患にあるのかは明らかでないこともあります。