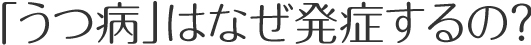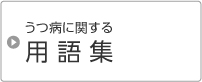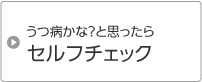「環境」と「脳」の関係に悪循環が生じます
仕事の量の増大・質の変化、裁量権の減少や人間関係などの社会環境の変化によるストレスと脳の働きによって「うつ病」が発症するといわれています。
ストレスになる出来事が重なったとき、周囲からサポートが十分に受けられない環境などが背景にあると、不安や不満が積み重なり、眠れない状態やいくら眠っても疲れがとれない状態が続きます。その結果、脳の機能が低下し、情報処理がうまくできなくなります。すると、次第にマイナス思考に陥り、自分はダメな人間だと自己否定したり、物事に対して消極的になったり、やがて活動量が減少していきます。そのため、以前はさほど感じなかった出来事に対してストレスを敏感に感じるようになり、否定的な考え方が支配します。再び不安が生まれ、眠れないという悪循環を繰り返します。
いくつかのストレスになる出来事が重なっているにもかかわらず、周りのサポートが十分に受けられない状態が続く。あるいは、そのように考える。
適切な睡眠がとれず脳の機能が回復しなくなる。
- 自分はダメな人間だと思う。
- 「どうせだめだ」と初めからあきらめる。
- 被害的な思考にとらわれる。
脳はストレスを処理できなくなり、うまく機能しなくなる。
- 「何もできていない」と自分を責める。
- 問題を避けて他のことに依存する (酒、インターネットなど)⇒やらなければならないことがたまってしまう。
ひとりで問題を抱え込んでしまう。
普段なら気にならなかったことまで「とても大変だ」と感じてしまう。ストレスと感じる出来事が増えて不安がつのり、睡眠がとれなくなったり、いつも眠たい状態が続く。
「日本うつ病学会治療ガイドライン:大うつ病性障害」より引用改変
「環境的要因」「身体的要因」も誘因になります
「うつ病」は、さまざまな要因が複雑に作用して発症すると考えられています。たとえば、人間関係のトラブル、親しい人との死別や離別などの喪失体験、家庭内不和、仕事や学業での行き詰まりなどの「環境的要因」、そして、慢性的な疲労、脳・神経疾患、その他重大な身体疾患、ホルモンバランスの変化、薬の副作用などの「身体的要因」もうつ病の引き金になることがあります。
しかし、はっきりとした誘因がなく発症することもあります。特に、慢性・再発性のうつ病にははっきりとした誘因が見当たらないことが多くあります。
環境要因
- 親しい人との死別や離別
- 仕事や財産の喪失
- 人間関係のトラブル
- 仕事や学業での行き詰まり
- 環境の変化
(就職、退職、転勤、離婚、妊娠、育児、
引っ越しなど、結婚、昇進などの吉事も含む)
身体的要因
- 慢性的な疲労
- 脳・神経疾患
(脳血管障害、パーキンソン病など) - 身体疾患(がん、甲状腺機能異常など)
- ホルモンバランスの変化
(月経前、出産後、更年期など) - 服用中の薬剤の影響
(ステロイド、経口避妊薬など)
うつ病
「うつ病」のカギは神経伝達物質
脳には神経細胞が無数にあります。これらの神経細胞は、神経伝達物質を介してからだやこころにさまざまな指令を伝えています。意欲や気分、記憶などに関するこころの調整は、神経伝達物質のセロトニンやノルアドレナリンを介して行われます。これらが神経細胞から放出されると受け手となる神経細胞の受容体に結合して指令が伝達され、感情をコントロールします。
しかし、過度のストレスや心身の疲労などで、神経伝達物質のセロトニンやノルアドレナリンが減少して十分に機能しなくなると、感情のコントロールができず、憂うつ感や無気力などを引き起こすといわれています。